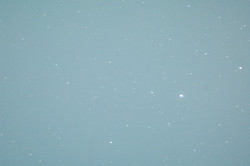ポータブル赤道儀 初めての実写テスト
カテゴリ<天体写真 ポータブル赤道儀 自作 ステッピングモーター>
「前回までの記事」10月5日、昨日までの連日の雨が止み、夕方北極星が見れるかも知れない。 そこで、今晩こそ、製作したポータブル赤道儀の実力試験を行おうと準備をしました。 結果は失敗でした。 まあ、最初からうまくいくのがおかしいという試験ですので、初めて行った失敗の記録と今後の課題を紹介し、これから何回もトライして、なんとか見れる天体写真撮影に挑戦していきます。
隣の空き地に3脚を建て、レッドドットファインダーの真ん中付近に北極星が来るように狙いを定めた後、天頂からやや西に傾いた1等星をめがけてカメラの位置を固定し、赤道儀は定速で追尾しながら60秒、90秒、120秒、150秒とシャッター開放時間を変更しながら撮影しました。 撮影しましたと言っても、そこまでたどりつくのに45分くらいかかっており、60秒の撮影は赤道儀のモーターがONしておらず星は完全な線になっていました。他の画像は一応追尾はしているのですが、極軸が合っていなく短い線になっていました。
赤道儀の回転テーブルとシャフトはDカットして2本のイモネジをしっかり締めたつもりでしたが、カメラの重みで3度くらいの遊びが生じ、星をカメラのファインダーの中央に持ってきて手を離すとずれてしまいます。
この場で対策が出来ないので、遊びの分だけずらしてセットし、手を離したとき、画面の中央付近にくるようにセッティングできるまで30分くらいかかりました。
その作業をやっている内に多分極軸合わせもずれてしまっていると思われますが、今夜はまず画像を残す事を最優先としました。
カメラがノイズリダクションの処理をしている事を忘れて、タイマーを仕掛けてシャッターONの信号をカメラに送ってもシャッターが開かず、あせりもあって、全ての画像のシャッター開放時間はバラバラです。
この晩は中秋の名月の前日で月がこうこうと輝いており、2等星以下の星は肉眼では見えない状況でしたので、カメラの背面にあるリアルタイムの液晶画面は明るい灰色で星はひとつも見えません。
左上はシャッター90秒開放、右上は150秒開放時の星画像です。 いずれも200mm望遠レンズで撮影しています。 画像を拡大すると判りますが、どちらも星は線状に流れています。
90秒の画像の星の軌跡が円弧状になっています。 これは極軸合わせのエラーに加えカメラが回転したのではないかと思われます。 各部の締め付けが弱かったの原因でしょう。
今回は初めての撮影でしたので、改善テーマが多すぎます。 特にカメラの位置をしっかり固定できるようにしないと、極軸合わせどころではなくなります。 また、レッドドットファインダーの精度はかなりいい加減で、北極星の時角を論議するレベルには到底達していません。
回転テーブルの遊びの問題は、2個のイモネジのゆるみでした。しっかり締めれば問題ないのを確認できましたが、また緩むようなら、イモネジを普通の長いビスに代えてネジ山の摩擦する面を増やす事にします。
レッドドットファインダーによる極軸合わせは200mmの望遠レンズでは難しいと理解しましたので、ドリフト法による極軸合わせを検討する事にします。